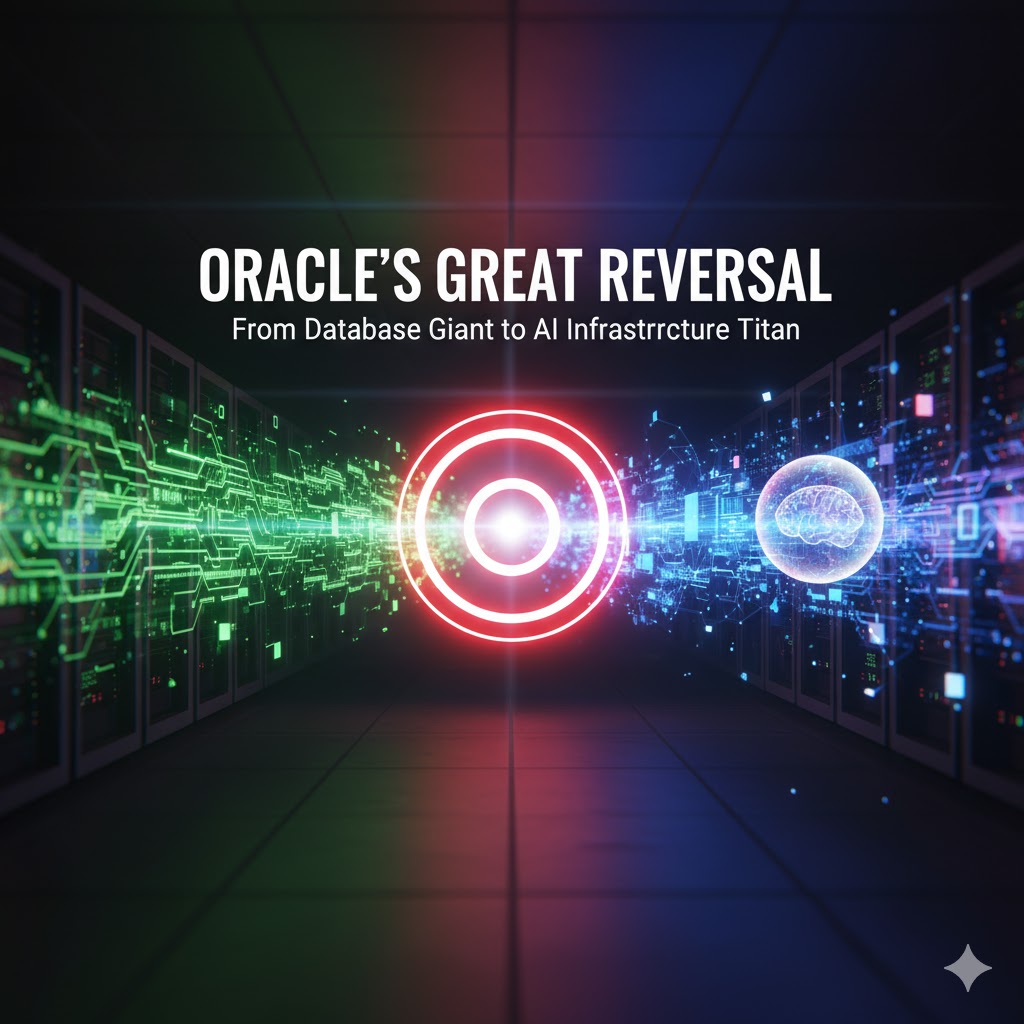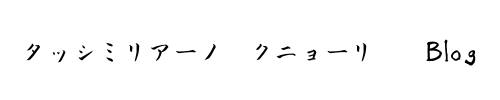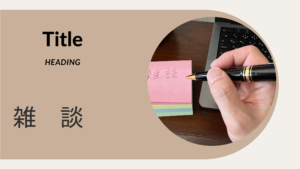オラクルの大逆転劇:『クラウド周回遅れ』から『AIインフの覇者』へ。なぜ今、世界が再びオラクルを選ぶのか?
序章:再評価される巨人
2024年から2025年にかけて、世界のテクノロジー業界で最も劇的な「再評価」を受けた企業を一つ挙げるとすれば、それは間違いなく「オラクル(Oracle Corporation)」でしょう。
多くのビジネスパーソンにとって、オラクルのイメージとは何でしょうか。 おそらく、「データベースの王様」「ラリー・エリソン」「大企業の基幹システム」といった、強力だが少し古めかしいキーワードが並ぶはずです。実際、2010年代のクラウドコンピューティング革命において、オラクルはAmazon(AWS)やMicrosoft(Azure)の後塵を拝し、「クラウド周回遅れ」とまで揶揄されていました。
しかし、2022年末に始まった生成AIブームが、そのすべての評価を一変させました。
ChatGPTを生んだOpenAIをはじめ、無数のAIスタートアップが、AIモデルを学習・実行するためのインフラとして、AWSやAzureではなく、オラクルのクラウド「OCI (Oracle Cloud Infrastructure)」をこぞって採用し始めたのです。
その結果、オラクルのクラウド事業の受注残(将来の売上が予約された額)は、2025年時点で天文学的な数字に膨れ上がりました。かつて「過去の巨人」と見なされかけた企業は、今や「AI時代の電力会社」という、最も重要なインフラプロバイダーとして、再び舞台の中央に躍り出たのです。
一体、オラクルに何が起こったのでしょうか? なぜ、彼らはこのAIという最大の波を掴むことができたのでしょうか?
その答えは、彼らが創業以来培ってきた技術的DNAと、クラウドへの遅れを取り戻すためにゼロから設計し直した「第2世代クラウド」のアーキテクチャ、そしてラリー・エリソンという希代の経営者の執念にあります。
本記事では、データベース帝国の誕生からクラウドでの苦戦、そしてAIインフラでの劇的な復活まで、オラクルの壮大な歴史と未来への展望を、10000字で徹底的に解き明かします。
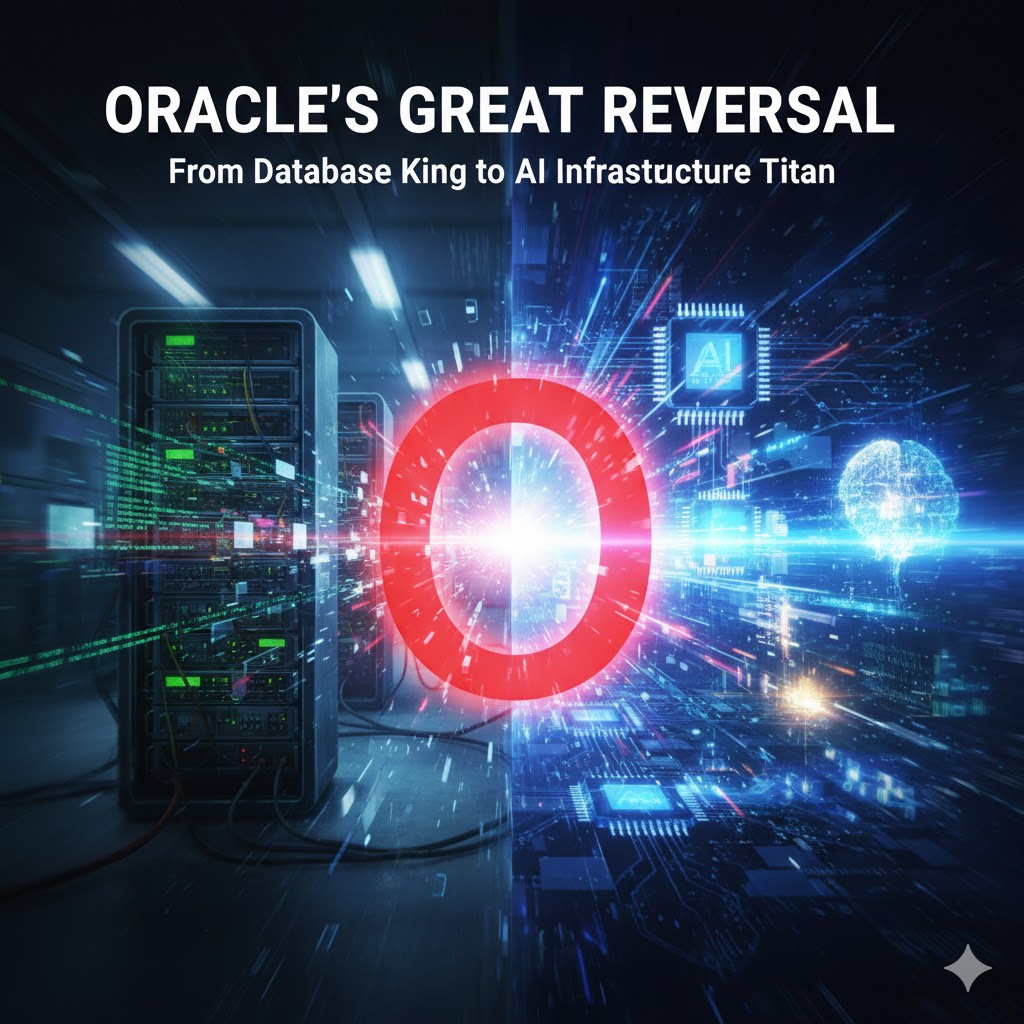
第1章:データベース帝国の誕生と栄光(1977年〜1990年代)
オラクルの物語は、常に一人の男、ラリー・エリソンを中心に展開します。
1-1. IBMの論文と「オラクル」プロジェクト
1970年代、主流のデータベースは「階層型」や「ネットワーク型」と呼ばれる、データの構造を柔軟に変更しにくいものでした。そんな中、IBMの研究者エドガー・F・コッドが、データを柔軟な「表(テーブル)」形式で扱う「リレーショナルデータベース(RDB)」という革新的な理論を発表します。
しかし、当時のIBMはこの理論をすぐには製品化しませんでした。理論は複雑で、当時のコンピュータの性能では実用的な速度が出ないと考えられていたからです。
このIBMの論文に可能性を見出したのが、ラリー・エリソン、ボブ・マイナー、エド・オーツの3人です。彼らは当時、アンペックス社でCIA向けの「オラクル」というコードネームのプロジェクトに携わっていました。彼らはこの理論こそが未来だと確信し、1977年に「Software Development Laboratories (SDL)」(後のオラクル)を設立します。
1-2. 世界初の商用RDBMS
彼らは、IBMがまだ研究段階だったRDBを、世界で初めて「商用製品」としてリリースすることを決意します。1979年、彼らは「Oracle V2」をリリース(V1はバグが多く実質的に存在しなかったためV2からとなった)。これが世界初の商用リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)となりました。
彼らの成功の鍵は、IBMが躊躇した「実装」をやり遂げたこと、そして「SQL(Structured Query Language)」というデータベース操作言語をいち早く採用したことでした。
さらに決定打となったのが、1983年の「Oracle V3」です。これを当時普及し始めていたC言語で書き直したことで、Oracleは特定のハードウェアに依存せず、DECのVAXミニコンからIBMのメインフレーム、さらにはUNIXワークステーションまで、あらゆるコンピュータで動作するという強力な「移植性」を手に入れました。
この戦略が大当たりします。企業はハードウェアを自由に選びながら、中核となるデータベースはオラクルを使い続けることができるようになりました。
1-3. 圧倒的シェアと「赤い巨人」
1980年代から1990年代にかけ、オラクルはその強力な製品と、ラリー・エリソンが率いるアグレッシブな営業部隊によって、世界中の大企業、金融機関、政府の基幹システムを席巻。「企業の重要なデータはオラクルにある」という時代を築き上げました。
日本でも1985年に日本オラクルが設立され、その地位は絶対的なものとなっていきます。企業のIT部門において、オラクルのロゴカラーである「赤」は、信頼性と高性能の象徴であると同時に、その高額なライセンス料と強気の交渉姿勢から「赤い巨人」として恐れられる存在にもなりました。
第2章:拡大戦略と「クラウドへの遅れ」(2000年代〜2010年代)
データベース市場を制覇したオラクルは、その莫大な利益を元手に、ITスタック全体を支配する帝国を築き始めます。
2-1. M&Aによる垂直統合
ラリー・エリソンは、データベース(インフラ)だけでなく、その上で動くアプリケーション(ERPやCRMなど)や、さらにはその下で動くハードウェアまで、すべてを自社で提供する「垂直統合」戦略を推進します。
その手段が、積極的なM&A(企業の合併・買収)でした。
- PeopleSoft (2005年): 人事・会計ソフトウェア(ERP)の雄。敵対的買収の末に獲得し、アプリケーション市場での地位を確立。
- BEA Systems (2008年): アプリケーションサーバー「WebLogic」を持つミドルウェアの強者を買収。
- Sun Microsystems (2009年): これが最大の買収の一つです。サーバー(SPARC)、OS(Solaris)、そして世界で最も広く使われるプログラミング言語「Java」を手に入れました。
これにより、オラクルは「ハードウェア(Sun)+ OS(Solaris)+ データベース(Oracle DB)+ ミドルウェア(WebLogic)+ アプリケーション(PeopleSoft等)」という、企業のITシステムを丸ごと提供できる、世界で唯一の企業となりました。
2-2. AWSの登場とオラクルの誤算
しかし、この垂直統合モデルが完成に近づいた2006年、IT業界の根底を覆す破壊者が登場します。Amazon Web Services (AWS)です。
AWSは「パブリッククラウド」という新しい概念を提示しました。企業は高価なサーバーやソフトウェアを自社で購入・所有(オンプレミス)するのではなく、インターネット経由で「利用した分だけ」ITリソースを借りればよい、というモデルです。
当初、ラリー・エリソンはこの動きを軽視していました。「クラウドなんて、ただの流行りだ」「セキュリティはどうするんだ」と公言し、自社の牙城である「オンプレミスでの高額なライセンス販売」というビジネスモデルを守ろうとしました。
これがオラクルの「クラウドへの遅れ」の始まりでした。
AWSが猛烈な勢いで成長し、MicrosoftがAzureで猛追する中、オラクルはようやく重い腰を上げますが、最初に提供した「第1世代クラウド」は、既存のオンプレミス製品を無理やりクラウドに乗せたようなもので、AWSやAzureの柔軟性や価格競争力には到底及びませんでした。
2010年代半ば、市場の評価は固まりつつありました。「オラクルは、メインフレーム時代のIBMがミニコン時代に対応できなかったのと同じように、クラウド時代に適応できない古い巨人だ」と。
第3章:OCIによる逆襲の狼煙(2016年〜)
このままでは負ける。ラリー・エリソンとオラクルの経営陣は、深刻な危機感を抱きます。そして、彼らはすべてをゼロから作り直すという、後発だからこそ可能な大胆な賭けに出ます。
それが、2016年頃から本格的に展開された「第2世代クラウド」こと「OCI (Oracle Cloud Infrastructure)」です。
3-1. AWSとAzureを徹底研究した「後発の利点」
OCIの開発チームは、AWSやAzureがなぜ成功したのか、そして彼らのアーキテクチャにはどのような弱点があるのかを徹底的に研究しました。
先行するクラウド(第1世代クラウド)は、サービス開始から10年以上が経過し、増改築を繰り返した旅館のように、古い設計に引きずられている部分がありました。特に、多くのユーザーが物理サーバーを共有する「仮想化」のオーバーヘッド(性能劣化)は、大規模な処理において弱点となっていました。
OCIは、以下の2つの明確な目標を掲げて設計されました。
- オラクルの最重要顧客(金融、通信など)がオンプレミスで使っている、最もミッションクリティカルなデータベース(Exadata)を、性能を一切妥協せずにクラウドで動かすこと。
- そのために、競合他社よりも「高性能」かつ「低価格」なインフラを提供すること。
3-2. OCIの心臓部:「オフボックス仮想化」
OCIの技術的な優位性を象徴するのが「オフボックス仮想化」というアーキテクチャです。
従来のクラウドでは、1台の物理サーバー内で、ユーザーの処理(アプリケーション)と、クラウド事業者の管理処理(ネットワーク仮想化、ストレージ仮想化など)が同じCPUを使って動いていました。これにより、他のユーザーが重い処理を始めると自分の処理が遅くなる「うるさい隣人(Noisy Neighbor)」問題が発生し、性能が安定しませんでした。
OCIは、この「管理処理」を、ユーザーが使うサーバー(CPU)から完全に切り離し(オフボックス)、専用のハードウェア(SmartNIC)に任せる設計にしました。
これにより、ユーザーはサーバーのCPU性能を100%占有でき、まるで物理サーバー(ベアメタル)を直接使っているかのような、安定した超高性能を得られるようになりました。
3-3. もう一つの切り札:「フラットネットワーク」
OCIはネットワーク設計も根本から見直しました。従来のクラウドネットワークが複雑な階層構造だったのに対し、OCIは「フラット」で「広帯域」なネットワーク(Closネットワーク)を採用しました。
これにより、どのサーバーからどのサーバーへも、非常に高速(低遅延)で通信できるようになりました。
この時点では、この2つの技術(オフボックス仮想化とフラットネットワーク)は、主にオラクルの本業である「データベース(Exadata)」を高速に動かすために設計されたものでした。
しかし、この設計が数年後、全く別の分野でオラクルを救う「切り札」となることを、彼ら自身も完全には予期していませんでした。
第4章:AIがオラクルを選んだ理由(2022年〜)
2022年末、OpenAIがChatGPTを公開し、世界は生成AIの時代に突入します。
AIモデル、特にChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は、その開発(学習)と実行(推論)に、膨大な数のNVIDIA製「GPU(Graphics Processing Unit)」を必要とします。
世界中の企業が、AI開発のために数千、数万個のGPUを確保しようと、クラウド事業者に殺到しました。ここで、スポットライトがOCIに当たります。
4-1. AI学習に最適だったOCIの設計
大規模なAIモデルの学習には、数千個のGPUを「あたかも一つの巨大なコンピュータのように」緊密に連携させる必要があります。GPU同士が超高速でデータをやり取りできなければ、学習は非効率になり、時間もコストも膨大にかかってしまいます。
ここで、OCIのアーキテクチャが完璧に噛み合いました。
- 超高速ネットワーク:OCIがデータベースのために設計した「フラットで低遅延なネットワーク」は、まさにGPU同士の大量通信(RDMA通信)に最適でした。
- 安定した性能:「オフボックス仮想化」により、ネットワークの性能が他のユーザーの影響を受けず安定していたため、大規模なAI学習を失敗なく実行できました。
AI開発者たちは気づきました。「OCIは、競合(AWS, Azure)よりも、大規模なGPUクラスタを高速かつ安定的に動かせる。しかも、価格が安い」と。
4-2. OpenAI、そしてAIスタートアップの選択
このOCIの優位性にいち早く目をつけたのが、他ならぬOpenAIでした。彼らはMicrosoft Azureをメインのインフラとしていますが、一部の重要なワークロード(AI学習)において、OCIの高性能なGPUクラスタも併用していることを公表しています。
さらに、Elon Musk氏が率いるxAIや、Adept、Reka AIといった著名なAIスタートアップも、こぞってOCIをAI開発基盤として採用しました。
理由は明確です。AIスタートアップにとって、GPUの利用コストは経営の死活問題です。OCIは、彼らにとって最も「コストパフォーマンスが高いAIインフラ」だったのです。
オラクルはNVIDIAとも強固なパートナーシップを結び、最新のGPU(H100, B200など)を誰よりも早く、大量に確保する戦略を取りました。
4-3. 劇的な財務状況の好転
このAIインフラ需要の爆発は、オラクルの業績に劇的な影響を与えました。 オラクルのクラウド受注残(RPO)は、市場の予想を遥かに超えるペースで増加し続け、株価も急騰。2025年10月には、受注残が4,550億ドル(約68兆円)というとてつもない規模に達したと報告され、市場を驚愕させました。
ラリー・エリソンは自信を持ってこう語ります。「我々は、AI産業にとっての『電力会社』のような存在になる」。
「クラウド周回遅れ」と揶揄されたオラクルが、AIという最大のテクノロジートレンドにおいて、最も重要なインフラプロバイダーの一社として、劇的な復活を遂げた瞬間でした。
第5章:オラクルの未来予想図:「マルチクラウド」という現実解
AIインフラで大成功を収めたオラクルですが、彼らは冷静に自社の立ち位置を分析しています。クラウド市場全体(特にSaaSや汎用的なPaaS)では、依然としてAWSとMicrosoftが巨大なシェアを握っています。
そこでオラクルが打ち出すのが、非常に現実的かつ強力な「マルチクラウド戦略」です。
5-1. 敵の懐に飛び込む「Oracle Database@Azure」
この戦略を象徴するのが、2023年に発表されたMicrosoftとの提携「Oracle Database@Azure」です。
これは、顧客が使い慣れたMicrosoft Azureのデータセンター内にいながら、あたかもAzureのサービスの一つのように、OCIが提供する高性能な「Exadataデータベースサービス」を直接利用できる、という驚くべき提携です。
多くの企業は、アプリケーションはAzure(またはAWS)で動かしているが、基幹データベースだけは高性能なオラクルを使いたい、というニーズを持っていました。オラクルはこのニーズに応え、「データベースだけなら、競合のクラウド上でも提供します」と門戸を開いたのです。
これは、「自社のクラウド(OCI)がすべて一番」という排他的な戦略ではなく、「顧客がいる場所(この場合はAzure)に出向いていき、自社の最強の武器(データベース)を売る」という、非常に柔軟かつ強力な戦略です。
5-2. AIとデータベースの融合
オラクルの未来は、この2つの柱によって支えられています。
- AIインフラ(OCI):高性能・低コストなGPUクラウドとして、AI企業や企業のAI部門の需要を取り込み続けます。
- データベース(Oracle Database):オンプレミス、OCI上、そして競合クラウド(Azure, AWS)上ですら、その絶対的な優位性を提供し続けます。
さらに、この2つは融合していきます。オラクルは自社のデータベースにAI機能(ベクトル検索など)を深く統合し、企業が持つ機密性の高い社内データを、安全なデータベース内で直接AIに活用させる戦略(RAG)を強力に推進しています。
結論:巨人は死なず。ただ、変貌するのみ
オラクルの約50年にわたる歴史は、まさに「変化への適応」と「技術的優位性の追求」の歴史でした。
リレーショナルデータベースという革新で時代を築き、 M&Aによる垂直統合で帝国を拡大し、 クラウドという大波に乗り遅れ、 そして、AIという次なる大波を掴むために、自らのクラウド基盤(OCI)をゼロから設計し直す。
彼らがOCIの設計において「データベース」という自社の原点(=最も重いワークロード)にこだわり、妥協のない高性能を追求したこと。それが偶然にも、数年後に到来する「AI」という、データベースをも凌駕する超高性能ワークロードの需要に完璧に応える結果となりました。
「データベースの王様」から「AIインフラの巨人」へ。 オラクルは、その強靭な技術的DNAをもって、最も劇的な変貌を遂げたテクノロジー企業として、再びIT業界の頂点に返り咲こうとしています。彼らの逆襲は、まだ始まったばかりです。